こんにちは 角田です!
今回はケアマネジャー様や利用者様からよく質問される「訪問リハビリって週何回やればいいんですか?」についてお答えします!
効果的な頻度の目安や決定時の重要ポイント、効果を最大限に引き出すコツを解説します。
1. 訪問リハビリの頻度を決める際に考慮すべき重要なポイント
訪問リハビリテーション(以下、訪問リハビリ)の頻度は、利用者様の生活の質(QOL)の維持・向上に直結する重要な要素です。しかし、「どのくらいの頻度で利用すれば効果的なのか」という疑問をお持ちの方も少なくありません。
ここでは、訪問リハビリの頻度を決定する際に考慮すべき、いくつかの重要なポイントについて解説します。
1.1 利用者様の状態や目標に合わせた訪問リハビリ頻度の考え方
訪問リハビリの頻度を決定する上で最も基本的なことは、利用者様お一人おひとりの心身の状態や、達成したい具体的な目標に合わせて計画することです。
画一的な頻度設定ではなく、個別性を重視したアプローチが求められます。
考慮すべき利用者様の状態には、以下のようなものがあります。
- 疾患の種類や重症度:脳卒中後遺症、骨折、パーキンソン病などの神経難病、呼吸器疾患、心疾患など、原因となる疾患やその進行度によって必要なリハビリ内容や量は異なります。
- 身体機能:筋力、関節の可動域、バランス能力、持久力、麻痺の程度などの評価に基づき、機能回復や維持に必要な運動量を考慮します。
- 日常生活動作(ADL):食事、更衣、入浴、整容、排泄、移動(寝返り、起き上がり、移乗、歩行など)といった、日常生活でどの程度の介助が必要か、あるいは自立を目指すのかによって頻度を調整します。
- 認知機能:理解力や記憶力、注意・集中力の状態も、リハビリの進め方や自主トレーニングの指導、頻度に影響します。
- 精神状態や意欲:リハビリに対するモチベーションや精神的な安定も効果を左右するため、利用者様のペースに合わせ、無理のない範囲で継続できる頻度設定が大切です。
また、利用者様やご家族がどのような生活を目指しているのか、具体的な目標を共有することが不可欠です。
「自宅のトイレまで一人で歩いて行けるようになりたい」「趣味だった散歩を安全に再開したい」「家族の介護負担を少しでも減らしたい」など、目標が明確であれば、それを達成するために必要なリハビリ内容と頻度が見えてきます。
訪問リハビリ開始前に作成される計画書において、これらの情報を基に担当の療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)とよく話し合いましょう。
1.2 介護保険と医療保険における訪問リハビリ頻度の違い
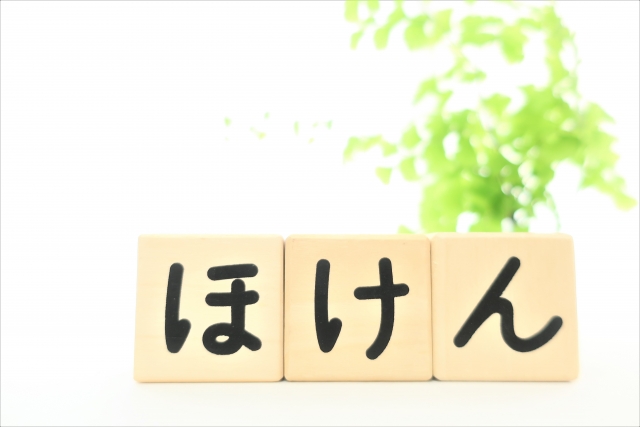
訪問リハビリは、利用する保険制度によって提供ルールや頻度の上限が異なります。
主に介護保険と医療保険の2種類があり、どちらの保険が適用されるかによって、利用できる頻度が変わってきますので注意が必要です。
介護保険と医療保険のどちらが優先されるかは、利用者様の状態や年齢などによって決まります。原則として、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方、または40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険が優先されます(介護保険優先の原則)。
| 保険の種類 | 対象者(主な例) | 頻度の目安・上限 | 1回あたりの時間 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方 | ケアプランに基づき決定されます。一般的に週1~3回程度が多いですが、状態に応じて調整可能です。1週間あたりの提供時間に上限(例:120分/週、これは1回20分のリハビリを週6回行った場合に相当)が設けられている場合があります。 | 通常1回あたり20分を1単位とし、40分(2単位)または60分(3単位)で提供されることが多いです。 |
| 医療保険 | 急性期後のリハビリが必要な方、厚生労働大臣が定める疾病等の方(例:パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症など)、がん患者の方、要介護認定を受けていない方など | 原則として1日に1回まで、週に3回までとされています。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七に掲げる疾病等の患者)(厚生労働省通知参照)に該当する場合や、病状の急性増悪などにより医師が特別指示(特別訪問看護指示書にリハビリの必要性を記載)を出した場合は、週4回以上の訪問や1日複数回の訪問が可能な場合があります。 | 医師の指示に基づき、通常1回あたり30分~90分の間で提供されます。 |
このように、適用される保険によってルールが異なるため、ご自身の状況がどちらに該当するのか、また利用可能な頻度はどの程度か、担当のケアマネジャーや医療機関の相談員、かかりつけ医に確認することが重要です。特に、退院直後や病状が不安定な時期、医療保険から介護保険への移行期などでは、制度の理解と適切な情報共有が求められます。
1.3 医師やケアマネジャーと相談して決める訪問リハビリの頻度

訪問リハビリの頻度は、利用者様やご家族だけで決定するものではありません。
専門的な知識を持つ医師やケアマネジャー、そして実際にリハビリを提供する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった専門職と十分に連携し、相談しながら決定していくことが最も重要です。これを多職種連携と呼びます。
まず、訪問リハビリを開始するためには、主治医による訪問看護またはリハビリテーション指示書が必要不可欠です。
医師は利用者様の医学的な状態を総合的に把握し、リハビリの必要性や適切な頻度について専門的な判断を行います。
指示書には、リハビリの目的、重点的に行うべき内容、推奨される頻度や期間などが記載されます。
介護保険を利用する場合、ケアマネジャーが中心となってケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
ケアプランには、訪問リハビリを含む様々なサービスが位置づけられ、その中で利用者様のニーズに応じた適切な利用頻度が検討されます。
ケアマネジャーは、利用者様の希望、心身の状態、ご家族の介護力、他のサービスの利用状況、介護保険の区分支給限度基準額などを総合的に考慮し、最適な頻度を含むケアプランの原案を提案します。
この原案をもとに、サービス担当者会議で関係者が集まり、最終的なプランを決定します。
そして、リハビリ専門職は、利用者様の具体的な状態評価(アセスメント)を行い、目標達成に向けた専門的な視点から、効果的なリハビリプログラムと頻度を提案・実施します。
定期的なカンファレンス(多職種連携会議)や日々の情報共有を通じて、これらの専門職間で利用者様の状態変化やリハビリの進捗を共有し、必要に応じてリハビリテーション計画書やケアプランを見直します。
利用者様にとって最も効果的かつ無理のない頻度を見つけ、維持していくことが、質の高い訪問リハビリを実現する鍵となります。
利用者様やご家族も、遠慮なく希望や疑問点を伝え、関係者全員で納得のいく頻度を設定していくことが大切です。
2. 訪問リハビリの効果的な頻度の目安 週に何回が適切か

訪問リハビリの頻度は、利用者様の状態や目標によって大きく異なりますが、効果を最大限に引き出すためには適切な目安を知ることが重要です。
一概に「週何回がベスト」とは言えませんが、ここでは一般的な目安や頻度ごとの効果、そして頻度を決める上での注意点について解説します。
2.1 一般的な訪問リハビリの頻度の目安は週1回から3回
訪問リハビリの頻度として最も一般的なのは週に1回から3回程度です。
これは、介護保険制度における訪問リハビリの提供時間や、利用者様の体力、生活リズムなどを考慮した結果、多くの場合この範囲に落ち着くためです。
具体的には、1回の訪問リハビリは通常20分を1単位とし、介護保険では1週間に合計6単位(120分)まで利用できるのが基本です。
この120分をどのように配分するかによって、週の回数が決まってきます。例えば、1回40分のリハビリであれば週3回、1回60分であれば週2回といった形になります。
ただし、これはあくまで目安であり、利用者様の状態や目標、医師の指示、ケアマネジャーとの相談によって最適な頻度は異なります。
特に医療保険を利用する場合や、特定の疾患をお持ちの場合は、この限りではありません。
2.2 訪問リハビリの頻度別 効果と目的を理解する
訪問リハビリの頻度によって、期待できる効果や主な目的は変わってきます。それぞれの頻度における効果と、どのようなケースに適しているのかを理解し、利用者様に合ったプランを検討します。
2.2.1 週1回の訪問リハビリ 効果と適切なケース
週1回の訪問リハビリは、利用者様の状態がある程度安定しており、維持期のリハビリや自主トレーニングの習慣化を目指す場合に適しています。主な効果と目的は以下の通りです。
- 効果:
- 現在の身体機能やADL(日常生活動作)の維持
- 自主トレーニングの内容確認と指導、モチベーションの維持
- 生活環境の評価と福祉用具の提案
- ご家族への介助方法の指導や相談対応
- 精神的なサポート、社会参加への意欲向上
- 適切なケース:
- 身体機能が比較的安定しており、大きな改善よりも維持を目的とする方
- 自主トレーニングを主体的に行える方、またはその習慣をつけたい方
- 介護者の負担軽減や、介助に関する専門的なアドバイスを定期的に受けたいご家族
- 他の介護サービス(デイサービスなど)も利用しており、訪問リハビリは補完的な役割を担う場合
週1回の頻度では、リハビリ専門職が直接介入する時間は限られるため、自主トレーニングの重要性がより高まります。
専門職は、その自主トレーニングが効果的に行えているかを確認し、必要に応じて内容を調整する役割を担います。
2.2.2 週2回の訪問リハビリ 効果と適切なケース
週2回の訪問リハビリは、身体機能の具体的な改善やADLの向上を目指す場合に効果的な頻度と言えます。週1回よりも専門職の介入が増えるため、より積極的なリハビリテーションプログラムを実施できます。
- 効果:
- 筋力、関節可動域、バランス能力などの身体機能の具体的な改善
- 食事、更衣、入浴、トイレ動作などのADLの向上
- 運動習慣の定着と体力の向上
- 痛みの軽減や管理
- より質の高い生活(QOL)の実現に向けた支援
- 適切なケース:
- 退院直後で、ある程度集中的なリハビリが必要なものの、毎日ではない方
- 明確な機能改善の目標があり、積極的にリハビリに取り組みたい方
- 週1回では効果が感じられにくい、または状態が悪化傾向にある方
- 新しい動作や技術の習得を目指す方
週2回の介入により、リハビリの成果が目に見えやすくなり、利用者様のモチベーション維持にもつながりやすいでしょう。また、状態の変化にも早期に対応しやすくなります。
2.2.3 週3回以上の訪問リハビリ 効果と適切なケース
週3回以上の訪問リハビリは、集中的な介入が必要な時期や、医療的なニーズが高い場合に選択されることが多い頻度です。特に、急性期病院や回復期リハビリテーション病院を退院した直後など、在宅生活への移行期に効果を発揮します。
- 効果:
- 短期間での集中的な身体機能の回復・向上
- 廃用症候群の予防と改善
- 重度の機能障害に対するアプローチ
- 嚥下障害やコミュニケーション障害に対する専門的なリハビリ(言語聴覚士による場合)
- ご家族への高度な介助技術の指導
- 適切なケース:
- 脳卒中後遺症、骨折後、神経難病など、集中的なリハビリが特に効果的な疾患の方
- 退院直後で、できる限り早期の在宅生活への適応を目指す方(特に「生活混乱期」を乗り越えるため)
- 状態が不安定で、頻回なモニタリングと介入が必要な方
- 医療保険での訪問リハビリの対象となる方(医師が週3回以上のリハビリが必要と判断した場合など)
脳卒中発症後の3~6ヶ月間は、機能回復のゴールデンタイムとも言われ、この時期に集中的なリハビリを行うことで、その後の生活の質が大きく変わる可能性があります。ただし、利用者様の体力や意欲、介護保険の支給限度額なども考慮して決定する必要があります。
以下に、一般的な訪問リハビリの頻度と目的、効果の目安をまとめます。
| 頻度 | 主な目的 | 期待される効果 | 適切なケース例 |
|---|---|---|---|
| 週1回 | 状態維持、自主トレ指導、環境調整、相談支援 | ADL維持、不安軽減、介護負担軽減 | 状態安定期、自主トレ主体、介護者の相談が主 |
| 週2回 | 機能改善、ADL向上、運動習慣化 | 身体機能向上、日常生活動作の改善、QOL向上 | 軽度~中等度の機能低下、退院後安定期、目標達成に向けた取り組み |
| 週3回以上 | 集中的な機能回復、重度化予防、早期社会復帰 | 大幅な機能改善、合併症予防、早期の在宅生活再建 | 急性期後、退院直後、集中的な介入が必要な状態 |
この表はあくまで一般的な目安です。個々の利用者様の状態やニーズに合わせて、柔軟に頻度を調整することが最も重要です。
2.3 訪問リハビリの頻度は多ければ多いほど効果的というわけではない理由
「リハビリは多ければ多いほど良い」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。過度な頻度の訪問リハビリが、かえって利用者様の負担になったり、自主性を損ねたりする可能性も考慮する必要があります。
- 体力的な負担: 特に高齢者や体力の低下している方にとって、頻繁なリハビリは疲労を蓄積させ、逆効果になることがあります。
- 受け身の姿勢の助長: 専門職が頻繁に関わることで、利用者様がリハビリに対して受け身になり、自主的な活動意欲が低下する恐れがあります。
- 費用対効果: 介護保険サービスには限りがあり、他の必要なサービスとのバランスも考慮する必要があります。費用に見合う効果が得られているか、定期的な見直しが求められます。
- 目標達成後の見直し: 設定した目標がある程度達成されたにも関わらず、同じ頻度でリハビリを続けることは、マンネリ化や依存を生む可能性があります。目標達成後は、頻度を減らしたり、自主トレーニング中心に移行したりすることも重要です。
- 生活リズムの制約: 訪問リハビリの時間が生活の中心となり、他の活動や休息の時間が十分に取れなくなることもあります。
大切なのは、利用者様の「その時の状態」と「目指す目標」にとって最適な頻度を見極めることです。リハビリ専門職やケアマネジャーが密に連携を取り、定期的にリハビリ計画を見直し、必要に応じて頻度を調整していくことが、効果的な訪問リハビリにつながります。
3. 訪問リハビリの効果を最大限に引き出すための頻度以外のコツ

訪問リハビリテーションの頻度もさることながら、その効果を最大限に高めるためには、頻度以外にもいくつかの重要なコツが存在します。
利用者様とご家族、そしてリハビリ専門職が一丸となって取り組むことで、より質の高い在宅療養生活を目指しましょう。
3.1 明確な目標設定とリハビリ計画の共有で効果的なリハビリを
訪問リハビリテーションを開始するにあたり、利用者様ご自身が「どうなりたいか」という具体的な目標を持つことが、リハビリテーションの成果を大きく左右します。
「一人でトイレに行けるようになりたい」「近所のスーパーまで買い物に行きたい」など、生活に根ざした目標は、リハビリへの意欲を高め、主体的な参加を促します。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職は、利用者様の状態や希望を丁寧に伺い、医学的な観点も踏まえて、実現可能な目標を一緒に設定します。
そして、その目標を達成するための具体的なリハビリテーション計画を作成し、利用者様やご家族、ケアマネジャー、医師など関係者間で共有することが不可欠です。計画の共有は、関わる全ての人が同じ方向を向いてサポートするための羅針盤となり、一貫性のある効果的なリハビリテーションの提供につながります。
3.2 自主トレーニングの併用で訪問リハビリの効果を高める
訪問リハビリテーションは週に数回、限られた時間で行われるため、リハビリ専門職が訪問しない日にも自主トレーニングを継続することが、効果を高める上で非常に重要です。専門職から指導された運動や生活動作の練習を、日常生活の中に無理なく取り入れることで、身体機能の維持・向上やリハビリ効果の定着が期待できます。
自主トレーニングの内容は、利用者様の状態や目標、安全性を考慮して専門職が個別に提案します。初めは簡単なものからスタートし、徐々にステップアップしていくことが長続きの秘訣です。
ご家族も声かけや見守りなどで協力し、安全に、そして楽しく取り組める環境を整えることが望ましいでしょう。ただし、痛みや体調不良を感じた場合は無理せず中止し、専門職に相談することが大切です。
3.3 ご家族の理解と協力が訪問リハビリの効果を左右する
在宅でのリハビリテーションにおいて、ご家族の理解と協力は、利用者様の精神的な支えとなるだけでなく、リハビリ効果そのものにも大きな影響を与えます。
リハビリの目標や内容、進捗状況をご家族と共有し、日々の生活の中での介助方法や声かけのポイントなどを一緒に学ぶことで、ご家庭全体でリハビリに取り組む体制を作ることができます。
例えば、リハビリ専門職が指導した動作を日常生活で実践する際の声かけや、安全な住環境の整備、自主トレーニングへの励ましなどが、ご家族にできる具体的な協力です。
また、リハビリの過程で見られる小さな変化や進歩を一緒に喜び合うことは、利用者様のモチベーション維持に繋がります。ご家族がリハビリチームの一員として積極的に関わることで、利用者様は安心してリハビリに集中でき、より良い成果が期待できるでしょう。
3.4 定期的な効果測定とリハビリ計画の見直しで最適な頻度を維持
訪問リハビリテーションの効果を確実なものにするためには、定期的な効果測定と、それに基づくリハビリテーション計画の見直しが不可欠です。
体力測定、日常生活動作(ADL)の評価、生活の質(QOL)に関する聞き取りなどを通じて、リハビリの成果や課題を客観的に把握します。
これらの評価結果を踏まえ、リハビリ専門職は医師やケアマネジャーと連携し、目標の達成度合いや利用者様の状態変化に応じて、リハビリ計画を柔軟に見直します。
このプロセスを通じて、リハビリの内容だけでなく、訪問頻度が適切であるかどうかも検証され、常に最適な状態でリハビリテーションが提供されるよう調整されます。介護保険制度においても、訪問看護またはリハビリテーション計画の作成や定期的な評価、利用者や家族への説明と同意が定められており、PDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)を回していくことが、質の高いリハビリテーションの基本となります。
4. 【事例紹介】訪問リハビリの頻度と効果的な活用例

訪問リハビリテーションは、利用者様一人ひとりの状態や目標に合わせて頻度を設定することが、効果を最大限に引き出す鍵となります。ここでは、具体的な事例を通して、訪問リハビリの頻度と効果的な活用方法について解説します。
4.1 事例1 脳梗塞後遺症 週2回の訪問リハビリで歩行能力が改善したケース
A様は70代男性、脳梗塞の後遺症により左片麻痺があり、屋内での杖歩行は可能でしたが、屋外歩行には不安を抱えていらっしゃいました。「もう一度、近所の公園まで散歩に行きたい」というご本人の強い希望があり、訪問リハビリを開始しました。
当初は週1回の訪問リハビリを検討しましたが、ご本人様の意欲の高さと、早期の目標達成を目指すため、理学療法士と相談の上、週2回(1回40分)の頻度で集中的にリハビリを行うことになりました。リハビリ内容は、主に以下の通りです。
- 麻痺側の筋力増強訓練
- バランス訓練
- 歩行訓練(屋内・屋外)
- 福祉用具(杖)の選定と使用方法の指導
- ご家族への介助方法の指導
リハビリ開始から3ヶ月後、A様の状態には以下のような変化が見られました。
| 評価項目 | リハビリ開始前 | リハビリ3ヶ月後 |
|---|---|---|
| 屋内歩行 | 杖を使用し、不安定ながら可能 | 杖を使用し、安定して可能 |
| 屋外歩行 | 介助があれば短距離可能だが、不安強い | 杖を使用し、付き添いのもと近所の公園まで歩行可能 |
| ご本人の自信 | 低い | 向上し、積極的に外出を希望 |
A様のケースでは、週2回という頻度で集中的に関わることで、運動学習が促進され、身体機能の改善と共に自信を取り戻すことができました。また、定期的なリハビリと自主トレーニングの組み合わせ、ご家族の協力が目標達成に繋がったと考えられます。
4.2 事例2 大腿骨骨折後 週3回の集中的な訪問リハビリで早期の自宅復帰を果たしたケース
B様は80代女性、転倒により大腿骨頸部骨折を受傷し、手術後、リハビリ目的にて入院されていました。退院後の生活に不安があり、特に自宅内での移動やトイレ動作の再獲得が課題でした。「できるだけ早く、元の生活に戻りたい」というご希望から、退院直後より訪問リハビリを開始しました。
B様の状態と目標を踏まえ、医師、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士が連携し、退院後1ヶ月間は週3回(1回60分)という高頻度での集中的なリハビリテーションを実施する計画を立てました。リハビリ内容は、主に以下の通りです。
- 関節可動域訓練
- 筋力増強訓練(特に患側下肢)
- 起立・着座訓練
- 歩行訓練(歩行器から杖への移行)
- 日常生活動作(ADL)訓練(トイレ動作、更衣動作など)
- 家屋環境の評価と福祉用具の提案
集中的なリハビリの結果、B様は以下のように改善されました。
| 評価項目 | 退院直後 | リハビリ1ヶ月後 |
|---|---|---|
| 歩行能力 | 歩行器にて室内監視レベル | 杖にて室内自立、短距離であれば屋外も可能 |
| トイレ動作 | 一部介助が必要 | 手すりを使用し自立 |
| 生活への自信 | 不安が大きい | 自宅での生活に自信がつき、意欲的に活動 |
B様のケースでは、退院直後の体力低下や廃用症候群の進行を防ぎ、集中的なリハビリによって早期に身体機能とADLを向上させることができました。
週3回という頻度は、ご本人様の体力的な負担も考慮しつつ、最大限の効果を引き出すための設定でした。この集中的な介入により、B様は目標であった早期の自宅での生活再建を果たすことができました。
これらの事例はあくまで一例であり、最適な訪問リハビリの頻度は利用者様の状態、目標、生活環境、利用できる保険制度などによって異なります。担当の医師やケアマネジャー、リハビリ専門職と十分に相談し、個別のリハビリテーション計画に基づいて頻度を決定することが重要です。
5. 訪問リハビリの頻度に関するよくあるご質問
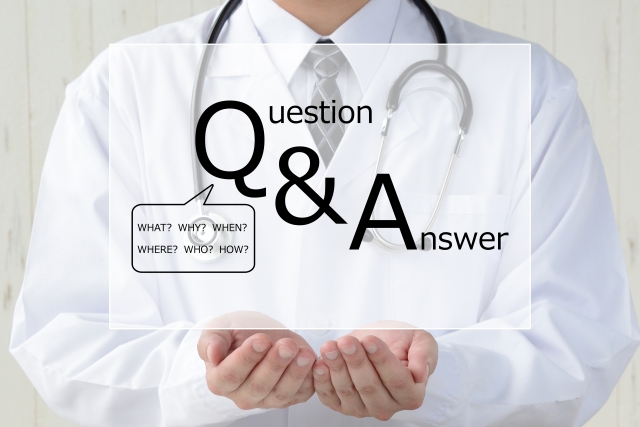
訪問リハビリの頻度や利用に関して、利用者様やご家族様から寄せられることの多いご質問とその回答をまとめました。
5.1 訪問リハビリ1回あたりの時間はどのくらいですか
訪問リハビリ1回あたりの時間は、利用者様の状態や目標、利用される保険制度によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。
| 保険の種類 | 1回あたりの一般的な時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 20分から60分程度 | ケアプランに基づき、通常は40分または60分で提供されることが多いです。制度上は1回20分以上と定められており、週に合計120分(例:20分×6回、40分×3回、60分×2回)が上限の目安となります。 |
| 医療保険 | 30分から60分程度 | 医師の指示に基づき、利用者様の状態やリハビリ内容に応じて決定されます。 |
実際の時間は、担当の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が、利用者様やご家族様、ケアマネジャーと相談の上、最も効果的なリハビリテーションが提供できる時間を設定します。
5.2 訪問リハビリの頻度を変更したい場合の手続きは
訪問リハビリの頻度を変更したい場合は、まずは担当のケアマネジャー、または主治医にご相談ください。利用者様の体調の変化、目標の達成状況、生活環境の変化などに応じて、リハビリ頻度の見直しを検討することができます。
手続きの一般的な流れは以下の通りです。
- 相談:ケアマネジャーまたは主治医に、頻度変更を希望する理由や現在の状況を伝えます。
- アセスメント・カンファレンス:必要に応じて、リハビリ専門職も交えて状態の再評価(アセスメント)や関係者間での話し合い(カンファレンス)が行われます。
- ケアプラン・指示の変更:介護保険の場合はケアプランの変更、医療保険の場合は医師からの指示変更が必要となることがあります。
- 新しい頻度での開始:手続きが完了次第、変更後の頻度で訪問リハビリが開始されます。
利用者様の同意のもとで進められるため、ご不明な点やご不安な点は都度確認するようにしましょう。
5.3 訪問リハビリの費用は利用頻度によってどう変わりますか
訪問リハビリ(看護)の費用は、利用する保険の種類(介護保険または医療保険)、1回あたりのリハビリ時間、そして利用頻度によって変動します。
基本的な考え方としては、以下のようになります。
| 項目 | 介護保険の場合 | 医療保険の場合 |
|---|---|---|
| 費用の基本 | サービス提供時間に応じた単位数で計算されます。頻度が増えれば、月々の総単位数も増加します。 | 診療報酬点数に基づいて計算されます。頻度が増えれば、月々の医療費も増加します。 |
| 自己負担 | 費用の1割~3割(所得に応じて変動)が自己負担となります。 | 年齢や所得に応じて定められた自己負担割合(例:1割~3割)を支払います。 |
| その他 | 事業所によっては、交通費が別途必要になる場合があります。 | |
具体的な費用については、契約時やケアプラン作成時に事業所から説明がありますので、必ず確認するようにしてください。また、月々の利用上限額や高額介護サービス費、高額療養費制度など、負担を軽減する制度もありますので、ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーにご相談いただくことをお勧めします。
6. まとめ
訪問リハビリの最適な頻度は、利用者様の状態や目標、利用する保険制度によって異なります。一般的には週1~3回が目安とされますが、医師やケアマネジャーと密に連携し、個別のリハビリ計画に基づいて決定することが最も効果的です。頻度だけでなく、明確な目標設定や自主トレーニングの継続も重要となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リハビタブルでは一緒に地域医療の発展を目指すメンバーを募集しています!
お電話でのご質問も受け付け中♪ ちょっと話を聞きたいというだけでもOK!
あなたが輝ける場所がここにあります!!
